当たり前を問い直すことは、学びの出発点
このブログでは、「当たり前を問い直すことは、学びの出発点です」というキーフレーズが何度も登場します。「なぜ、ぐるっと1週は360°なのか?」「なぜ、10進法でものを数えるのか?」等々の発問を授業で行っていることを紹介しています。
その「なぜ、10進法でものを数えるのか?」の中で、「10進法は当たり前すぎるのです」と書いていますが、本当に人類にとって、10進法は当たり前なのでしょうか?
日本語で数を数えてみると、
一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二……
のように、明らかに十進法です。
ところが、英語では少し違います。
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve thirteen, fourteen,……
と、twelveの12までは、繰り上がりなしに数えます。つまり、12進法です。
ところが、13は、twelve-oneではなく、thirteenと\(3+10\)のような10進法表記になります。以下、nineteenまで続いて、\(20\)はtwentyと\(2\times10\)のような十進法表記です。つまり、英語はtwelveまでは12進法で、それ以降は10進法ということになります。
なぜtwelveまでは12進法なのか?
英語圏では、12進法が多く見られます。
物の数を表すダース (12)、グロス (144 = 122)、グレートグロス (1728 = 123)、スモールグロス (120 = 12×10) という単位があり、西洋で用いられる。1971年2月15日まで、イギリスポンドは、1 ポンドは 240 ペンスであり、12 ペンスが 1 シリング、20 シリングが 1 ポンドであった。
この他にも、ヤード・ポンド法は十二進法が主流であり、長さの 1 フィート = 12 インチ = 144 ライン = 1728 ポイントである。同じく、1 トロイポンド = 12 トロイオンス = 144 スカラプル = 1728 シードである。プラモデルの縮尺に 1/144 (= 12-2) が多いのも、12 フィートすなわち 144 インチを逆数にしたサイズが由来である。
https://ja.wikipedia.org/wiki/12進法
このように、計ったり、数えたりする際は、10のかたまりを作るより、12のかたまりを作った方が、あつかいやすく、広く交易等で使われていたようです。それは、10より12の方が約数が多く、分割しやすかったということでしょう。(そもそも、「ラジアン」って何ですか?参照)
人類の数え方を巡る試行錯誤の痕跡
英語の数の表記に、12進法の痕跡がのこっているのは、こうした歴史が刻まれているのでしょうね。私が中学校で英語の数の数え方を憶えて以来数十年。1年間のアメリカ留学も経験しているのに、今日まで、実は気づきませんでした。
こうしてみると、「なぜ、10進法でものを数えるのか?」の中で、「10進法は当たり前すぎるのです」と書きましたが、長い人類の歴史の中で考えると、決して、10進法は当たり前ではなかったようです。
人類の認識は、理路整然と一直線進化してきたわけではありません。長い歴史の中で、数え切れない試行錯誤が行われ、淘汰されたものが現在に引き継がれ、それを私たちが学んでいます。
よく観察すれば、当たり前と思っているものの中に、そうした人類の壮大な試行錯誤の痕跡が見られることは、とても面白いことです。
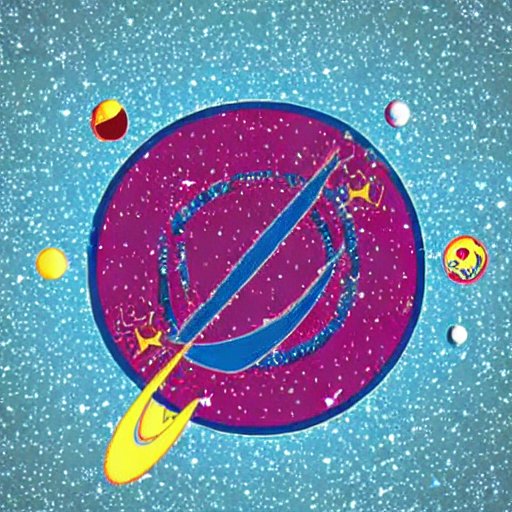


コメント