2022年度から導入が始まった「観点別評価」
高校では、2022年度の1学年から新しい学習指導要領が施行され、年度進行で導入が進んでいます。2023年度は、1, 2学年が新しい学習指導要領の元で教育が行われています。
観点別評価とは、「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点から児童生徒の学習状況を評価するものです。それをれをA, B, Cの3段階で評価し、それらを総合して評価します。
最初の2つは、テストを工夫すれば客観的に測定可能だと思われます。現場が困惑し混乱しているのは、「主体的に学習に取り組む態度」の評価です。
「主体的に学習に取り組む態度」をどうやって評価せよというのか?
「主体的に学習に取り組む態度」を評価する上での困難は、
- どの程度「主体的」に取り組んでいるかを数値化する困難
- 「態度」を数値化する困難
の2つがあります。
その結果、評価の基準は曖昧になり、教師によって評価がばらばらになる、評価する日の教員の気分によって評価が異なるなどの問題が生じます。
文部科学省の評価方法の例示
文部科学省は、評価方法について以下のように例示しています。
「主体的に学習に取り組む態度」の具体的な評価の方法としては、ノートやレポート等における記述、授業中の発言、教師による行動観察や、児童生徒による自己評価や相互評価等の状況を教師が評価を行う際に考慮する材料の一つとして用いることなどが考えられる。
児童生徒の学習評価の在り方について(報告)
授業中の発言については、高校では残念ながら主体的に行われることは少なく、評価の材料にはなりにくいし、指名した場合の発言について、授業中に評価して記録することは、現実的ではありません。「教師による行動観察」も客観性を欠き、その生徒の性格(外向的、内向的等)や教師との関係性(生徒がどの程度その教師を信頼しているか)によって大きな違いが出ますから、評価になじみません。「児童生徒による自己評価や相互評価等の状況」も、参考資料程度の位置づけしか与えられません。
残るのは、「ノートやレポート等における記述」ということになります。
そのため、今、高校では、学力をつけるためではなく、「評価をするため」に課題が出され、提出物に生徒が追われ、教員もその評価に疲弊しています。
提出物で「主体的に学習に取り組む態度」が計測できるか?
現実的に現場で起こっていることをリアルに説明します。提出物を評価する際、例えば、次の4段階で評価するとします。
- A しっかりと主体的に取り組んでいる
- B 普通に取り組んでいる
- C 取り組みが不十分・提出期限が守られていない
- D 未提出
実際に評価してみると、B, C, Dの区別はある程度自信を持って判断できます。しかし、AとBは極めて微妙です。「消しゴムで消した跡がたくさん残っているなど、一生懸命問題と向き合っているように見えるが、字が汚く乱雑」、「非常にキレイにまとめられているが、答を上手に写しているようにも見える」などの判断は、極めて主観的になります。教員によって異なるのはもちろん、同じ教員でも大きなブレが生じ、何度も比較し直すなどの作業が必要になり、ストレスもたまるし、時間もかかります。
そのようにしっかり時間をかけて評価したとしても、あとから、「なぜこのレポートはAの評価で、このレポートはBの評価なのか説明して欲しい」などと言われたら、説明できない場合がほとんどではないでしょうか。「消しゴムで消した跡がなく、答を上手に写していると判断してBにした」などと説明して、親から「消しゴムで消した跡がないのは、学力があってスラスラと問題が解けたからだ。答を写したというのは失礼千万だし、証拠はあるのか」などと言われると、もうお手上げです。
- A 普通に取り組んでいる
- B 取り組みが不十分・提出期限が守られていない
- C 未提出
の3段階にすると、ほとんどの生徒がA評価になり、評価に差がつきません。
教師は疲弊している
あとから説明を求められた場合、ある程度きちんと説明ができるようにと、教員は1枚のプリントの評価にも膨大な時間をかけています。提出物の評価地獄で、超過勤務が常態化し、ストレスを抱えて、教員は疲弊しています。
生徒は課題地獄で、「答え丸写し症候群」に陥る
一方、生徒は、評価のために膨大な課題が各教科から出されるために、課題の提出に追われています。追い込まれると、答を上手に丸写しして、期限内になんとか提出せざるを得なくなります。これを3年間繰り返すと、いつの間にか「勉強」=「答を写すこと」=「無意味で苦痛」ということになりかねません。「主体的に学習に取り組む態度」を評価するための課題が生徒から主体性を奪い、生徒は自分で考えず、安直に答を見たり写したりする誤った「態度」を身につけてしまいかねません。
学校と生徒を守るために、「主体的に学習に取り組む態度」の評価に工夫を
若くて真面目な教員ほど、「主体的に学習に取り組む態度」を真面目に評価しようとして、苦しんでいます。一刻も早く、このような馬鹿げた制度は改めて欲しいと願いますが、まだ始まったばかりです。生徒と教員を疲弊から救うために、「主体的に学習に取り組む態度」を評価するための工夫をすることが大切です。
例えば、テスト範囲や提出課題を「必ず取り組む基本事項」と「主体的に取り組む課題」に分けて、「主体的に取り組む課題」に取り組むかどうかは、生徒本人が選択するようにしてはどうでしょうか?
「必ず取り組む基本事項」だけで、しっかりと取り組んでいたらBが取れるようにした上で、テストで少し「主体的に取り組む課題」からも出題して、できていれば、「主体的に学習に取り組む態度」の評価を少し上げるなどすれば、かなり客観性が出るし、教員の負担も減ります。
学ぶ歓び・教える歓びを取り戻そう!
本来、学ぶことは人間にとって大きな歓びです。それに関わることができる「教える」という営みも楽しいはずです。しかし、道理のない教育「改革」の押しつけて、学校から歓びが奪われつつあります。
このブログでは、数学教育において、学ぶ歓び、教える歓びを取り戻す、具体的な方策や学び方・教え方の知恵を提案します。
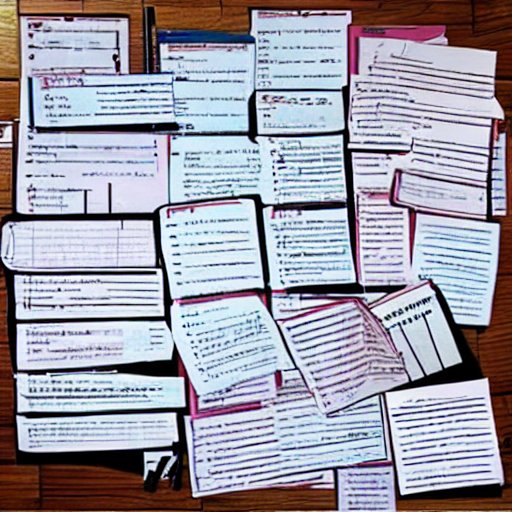


コメント